社労士の勉強をしていると、似たような用語がたくさん出てきて混乱しますよね。
今回取り上げるのは、「給付基礎日額」と「休業給付基礎日額」。
名前がそっくりですが、制度も使い道も違うので、しっかり区別して覚える必要があります。
目次
✅ ざっくり違いを言うと…
| 用語 | 使われる保険制度 | 主な給付 | 何を基準にしている? |
|---|---|---|---|
| 給付基礎日額 | 労災保険 | 休業補償、障害補償、遺族補償年金など | 災害前3か月の賃金 |
| 休業給付基礎日額 | 雇用保険 | 育児休業給付、介護休業給付など | 休業前の賃金(6か月など) |
✅ 給付基礎日額とは?(労災保険)
労働者が仕事中にケガをしたり、通勤途中に事故にあった場合に支給される労災保険の給付額の計算基礎になります。
たとえば、労災で休業した場合に支給される「休業補償給付」はこの額をもとに計算されます。
▷ 算定方法(基本形):
災害発生日の直前3か月間の賃金総額 ÷ その日数
※通勤手当なども含まれるケースがあります
✅ 休業給付基礎日額とは?(雇用保険)
こちらは、育児や介護など私的な理由で休業したときに支給される雇用保険の給付額の基礎になります。
たとえば、育児休業給付は休業前の賃金の67%が支給されますが、この「67%」の元になるのが休業給付基礎日額です。
▷ 算定方法(例):
休業前6か月間の賃金を平均して日額に換算
✅ 違いをわかりやすく図で比較!
| 観点 | 給付基礎日額 | 休業給付基礎日額 |
|---|---|---|
| 保険制度 | 労災保険 | 雇用保険 |
| 主な給付 | 休業補償給付、障害補償給付など | 育児休業給付、介護休業給付など |
| 賃金の期間 | 直前3か月間 | 休業前6か月間など |
| 支給割合の例 | 60%+特別支給20%(休業補償) | 67%(育児・介護) |
✅ 試験ではここが狙われる!
- 「給付基礎日額は雇用保険で使う」→ ❌(労災です!)
- 「休業給付基礎日額は労災で使う」→ ❌(雇用保険です!)
名前が似ているので、制度ごとにしっかり区別して覚えるのがポイントです。
✅ まとめ
- 「給付基礎日額」は労災保険で使う
- 「休業給付基礎日額」は雇用保険で使う
- 計算のベースになる期間や割合も違う
- 試験でも実務でも混同注意!
📘今後も社労士試験や制度理解に役立つ記事をゆっくり発信していきます。
同世代の学び直し仲間、ぜひ一緒にがんばりましょう!
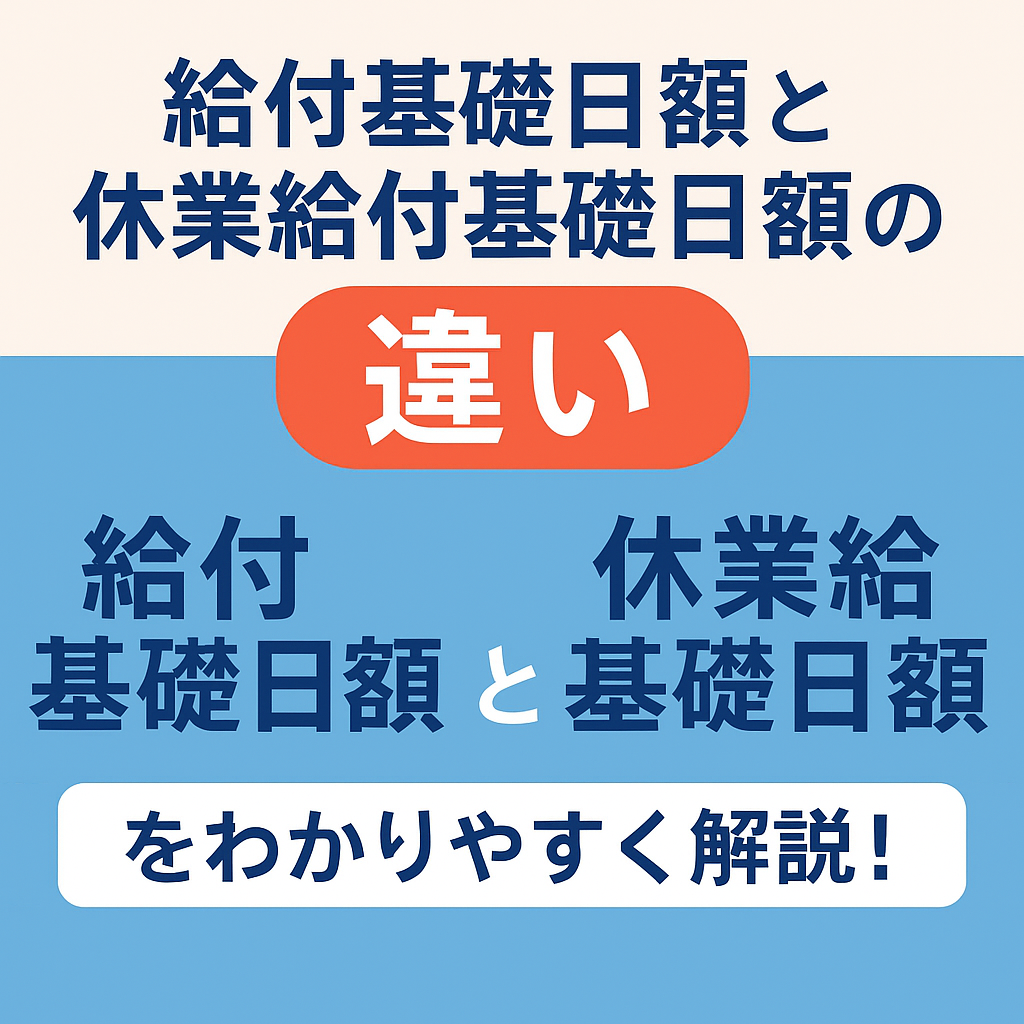
コメント